最近の一級建築士製図試験の採点割合は、「図面」:「計画の要点(記述)」=6:4と言われており、計画の要点(記述)が非常に重要であることが分かります。
また、ランクⅡで不合格になる方は、記述で上手く解答できていないことが多いです!
そこでこの記事では、令和5年度一級建築士製図試験「図書館」で著者が解答した「計画の要点(記述)」を公開&解説をします!
「この記事を読むメリット」
- 合格者の「計画の要点(記述)」を知ることができる!
- 別解答として何が考えられるかを知ることができる!
「計画の要点(記述)」は、図面との整合性が必須なため、図面(再現図)をご覧になっていない方は、下記の記事を見てからをオススメします!
≫【合格者の解答図面公開&解説! 令和5年度一級建築士製図試験「図書館」】はこちらから
「計画の要点(記述)」の再現図
下記に示すのが、試験当日の「計画の要点(記述)」を再現した図になります。
設問ごとに解説していきます。

(1)一般開架スペースについて
①蔵書数の確保及び書架等のユニバーサルデザイン
著者の解答

別解答として考えられること
蔵書数の確保
- 書架の蔵書面積(単独書架)は、180冊/㎡程度必要なため、蔵書面積 = 50,000冊 ÷ 180冊/㎡≒280㎡程度確保した。
書架等のユニバーサルデザイン
- 閲覧スペースにおいては、車椅子使用者でも通行できるように、書架と閲覧席間を1.2m以上確保する計画した。
- 書架にピクトグラムによる案内図を設け、車椅子使用者でも見やすい1,200mmの高さに配置した。
書架の蔵書面積(単独書架)は、170〜180冊/㎡必要です。
②敷地及び周辺条件(自然採光の活用を含む。)
著者の解答

別解答として考えられること
- 一般開架スペースに北向きのトップライトを設けることで、自然採光に配慮し、天井から柔らかな光が届くように計画した。
- 車の排気ガスや騒音に配慮して、「公共駐車場」側には開口部を設けない計画とした。
隣接している「公園」「店舗付き集合住宅「公共駐車場」への対応が求められたと考えられます。
(2)施設の機能構成、配置・動線計画について
①一般開架スペース、児童開架スペース及び企画展示スペースにおける多世代の交流
著者の解答

別解答として考えられること
- 一般開架スペースを2層で計画し、児童開架スペースや企画展示スペースの活動が見えるように配置することで、多世代との交流を促す計画とした。
- 自習室を2階・3階と分散配置で計画することにより、多世代で利用しやすくなるように計画した。
- 間仕切壁を設けないオープンな空間とすることにより、気軽に立ち寄ることができ、幅広い世代が交流できるように配慮した。
②施設の運営管理
著者の解答

別解答として考えられること
- エントランスホールに面して管理事務室を配置し、受付カウンターを設けることで、目視で監視ができる計画となり、セキュリティーに配慮した計画とした。
- 東側に管理ゾーンをまとめて計画し、西側に利用者ゾーンをまとめて計画した。このことにより、明確にゾーニング分けができ、動線交差を防ぎ、運営しやすい計画とした。
(3)一般開架スペースにおける空調方式について
空調方式、採用した理由及び配慮したこと
著者の解答

別解答として考えられること
空冷ヒートポンプパッケージ方式床置きダクト接続型+全熱交換器
- 成績係数が高く、省エネルギー性が高い、空冷ヒートポンプパッケージ方式床置きダクト接続型を採用することにより、スペース全体の温度分布が均一になるように計画した。
- 換気は全熱交換器を採用することにより、排熱を効率よく回収し、新鮮な空気に移すことで熱負荷を低減する計画とした。
単一ダクト方式
- 書籍の保存・管理に適した温湿度調整ができ、大空間の空調にも対応できるため、「単一ダクト方式」を採用した。
- ペリメーターゾーンの空調負荷に対応するために、窓付近の天井には線状吹出口(スロット型)を設けることで、快適な読書空間になるように計画した。
設備が指定された時のために「空冷ヒートポンプパッケージ方式」「単一ダクト方式」双方の記述を書けるようにしておくと良いと思います!
(4)屋上等に設置する設備について
配置計画において考慮したこと(①太陽光パネル、②キュービクル、③設備配管取出し口(はと小屋)、④空調室外機等)
著者の解答

別解答として考えられること
- 「はと小屋」は、横引き配管をできるだけ短くするためにPSの近くに設ける計画とした。
- 「はと小屋」と「空調室外機」を近接させることで、熱損失を低減し、省エネルギー性に配慮した。
「屋上設備の配置」についての記述が、初めて出題されました。今後も出題される可能性があるので、しっかり確認しておきましょう!
(5)省エネルギー化・エネルギー自立度について
省エネルギー化の実現及び再生可能エネルギーの導入によるエネルギー自立度を高めるために、建築・設備で配慮したこと
著者の解答

別解答として考えられること
- 屋上緑化を行うことで植物の蒸散作用が起こる。これにより、空気が冷却され、屋上からの日射熱の侵入を抑制し、空調負荷を抑制する計画とした。
- 一般開架スペースの高天井上部に「開閉式トップライト」を設けることで、自然採光を積極的に取り入れ、換気促進を図ることで省エネルギー化を実現した。
- 倉庫や廊下等の照明器具は人感センサー付きにするこで、人がいない時間帯は節電され、電力消費量を削減できるように計画した。
- トイレの雑排水に雨水を活用することで、水道使用量を削減し、エネルギー自立度が高くなるように配慮した。
問題に「ただし、太陽光パネル、LED照明、Low‒Eガラスに関する記述は除く。」という文言があり、この3つについては、記述が書くことはできませんでした。
(6)二酸化炭素の排出量削減について
建築物の材料や施工方法等において、二酸化炭素の排出量削減について考慮したこと
著者の解答

別解答として考えられること
- 既存建築物撤去範囲内は、CO2排出量を低減する地盤改良工法を採用することで、二酸化炭素排出量削減に配慮した計画とした。
「二酸化炭素排出量削減」についての記述は、今後も問われることが考えられるため、確認しておきたいです!
(7)閉架書庫の構造計画について
①一般開架スペースとの違いや構造的特徴 ②それらを踏まえて考慮したこと
著者の解答

別解答として考えられること
①-1:集密書架を設ける閉架書庫の方が単位床面積あたりの収蔵量が多く、積載荷重が大きい。
②-1:小梁の間隔を2.4m以下で計画し、連続梁とすることで、耐久性に配慮した。
①-2:1㎡に対する書架の荷重が大きいため、スラブの長期たわみやひび割れが生じやすい。
②-2:閉架書庫のスラブは200mmとし、ダブル配筋とすることで、たわみやひび割れを抑制した。
まとめ
今年度(令和5年)の記述は「屋上設備の配置計画」について、去年(令和4年)は「ペリメーターゾーンの断面詳細図」について初めて出題されました。
このように今後も「設備」について問われることが予想されます。また昨今、SDGsやカーボンニュートラルが話題になっており、「二酸化炭素排出量削減」についても引き続き問われることが予想されます。
しっかりと対策していきましょう!

下記に令和5年度(2023年度)一級建築士製図試験「図書館」のまとめ記事を示すからぜひ見に来てね!
「課題文の読み取り」「エスキス」「合格図面」について掲載してるよ!
最後に…おすすめの通信講座「Studying」
独学の方や金銭的に資格学校に通うことが難しい方に「Studying」がオススメです!
スマホやPCで動画講義が見れるので、隙間時間に学習できます!
無料講座もあるので、ぜひ下のリンクから試してみてください!







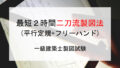
コメント